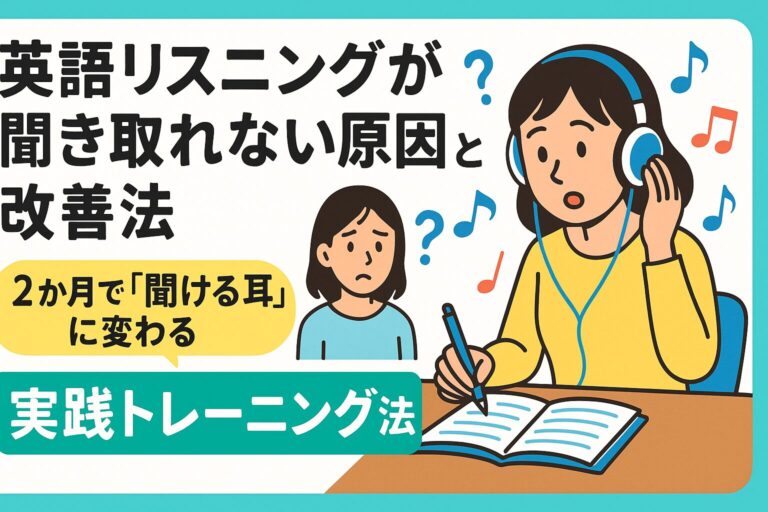「英語の音声を聞いても、単語がつながって何を言っているのか分からない」「TOEICのリスニングで点数が伸びない」──そんな悩みを抱えていませんか。
実は、私自身も同じように悩んでいました。学生時代は文法や単語を一通り勉強していたのに、いざネイティブの会話を聞くと、まるで別の言語のように感じたのです。スクリプトを読めば理解できるのに、耳では全く追いつかない。そんな状態が長く続いていました。
しかし、あるきっかけで「英語を聞き取るには音の知覚を鍛える必要がある」ことを理解し、練習方法を変えた結果、たった2ヶ月でリスニングが格段に向上しました。特別な才能や留学経験がなくても、正しい順序でトレーニングすれば誰でも英語の音は聞き取れるようになります。
この記事では、英語リスニングが聞き取れない原因を明確にし、実際に効果のあった改善法をステップごとに紹介します。机の上だけで終わらない「耳を使う学習法」で、英語が自然に理解できる耳を作りましょう。
コンテンツ
第1章 英語が聞き取れない本当の原因とは?
日本語と英語の「音の構造」の違いを理解する
英語が聞き取れない最大の原因は、単語や文法の知識不足ではなく「音の構造」にあります。というのも、日本語と英語では音の作り方がまったく異なるからです。日本語は一音ずつ明確に発音されるのに対し、英語は単語同士がつながり、音が省略されたり変化したりします。たとえば “want to” が “wanna” に、“did you” が “didja” のようになることがあります。
こうした音の連結や変化を「リエゾン」と呼びますが、これを知らないままリスニングをしても、ネイティブの発音がバラバラに聞こえてしまいます。つまり、聞き取れないのは「知らない単語」ではなく「知っている単語が音として認識できない」状態なのです。そのため、単語帳を増やすよりも、まずは英語の音のルールを理解することがリスニング改善の第一歩になります。
さらに、英語では強弱のリズムも重要です。意味を伝えるキーワードだけを強く発音し、それ以外は弱く短く流します。日本語のように均等に発音しないため、弱音が聞こえにくくなります。これが「聞き取れた気がしない」という感覚を生む原因です。
「脳の処理速度」が追いついていない
リスニング中に音が次々と流れていくと、頭の中で日本語に訳そうとして混乱することがあります。これは「脳の処理速度」が英語のスピードに追いついていないサインです。英語は単語の順序で意味を理解する言語のため、聞きながら同時に理解する力が求められます。
たとえば、日本語では「私は昨日、友達と映画を見た」と語順が自由ですが、英語では “I watched a movie with my friend yesterday.” のように順番が固定されています。聞きながら後半の意味を予測する処理をしていないと、最後まで理解が追いつきません。これがリスニング中に「途中で迷子になる」原因です。
解決法は、英語を日本語に訳さず「英語のまま理解する」練習をすることです。最初は難しく感じますが、短いフレーズを何度も聞くことで脳が英語の語順に慣れ、音を処理するスピードが上がります。その結果、英文を逐一訳さなくても意味がつかめるようになります。
「リスニング練習の順序」が間違っている
多くの学習者が見落としているのが「リスニング練習の順序」です。いきなり長文やニュース音声を聞こうとしても、聞き取れないのは当然です。リスニングには段階があり、「音→単語→フレーズ→文→会話」というステップを踏むことで少しずつ聞き取れる範囲が広がります。
たとえば、最初の段階では単語の発音を正確に認識すること。次に、2〜3語の短いフレーズを何度も繰り返し、音のつながりを体感します。そのうえで、短い文章や簡単な会話を聞く練習に進むと、脳が混乱せずに音を処理できるようになります。
私自身、以前はTEDや映画を教材にしていましたが、ほとんど聞き取れず挫折しました。ところが、1日10分のシャドーイングを短文で続けたところ、数週間で「英語が音として聞こえる」感覚をつかめました。つまり、リスニング改善には正しい順番があり、それを守ることで誰でも確実に伸びるのです。
第2章 音を聞き取る耳を作る具体的なトレーニング法
ステップ① 音の変化に慣れる「発音模写」トレーニング
英語を聞き取れるようになるための最初のステップは、「発音を正確に再現できるようになること」です。なぜなら、人は自分が再現できない音を聞き分けることができないからです。つまり、リスニング力の土台はスピーキングにあります。
おすすめは、ネイティブの音声を聞きながら1文ずつ「そっくり真似る」発音模写(オーバーラッピング)です。最初は英語ニュースやアプリ教材のようにスクリプトがある音声を使いましょう。文字を見ながら声に出して読むと、どの音がつながり、どこが消えているのかが明確に分かります。たとえば “I want to go.” の “to” がほとんど聞こえないなど、実際の音と文字のギャップに気づけます。
この練習を1日10分でも継続すると、英語のリズムが自然と身につきます。慣れてきたらスクリプトを見ずに同じ音声を真似し、発音やイントネーションを体で覚えましょう。これにより、リスニング時に「音の地図」が頭に描けるようになり、聞き取れる範囲が一気に広がります。
ステップ② 「ディクテーション」で音と意味を一致させる
次に行うべきは、英語の音を聞いて書き取る「ディクテーション」です。これは聞き取りの弱点を明確にする練習法で、音の抜けや聞き間違いを可視化できます。教材としては、ニュースや教材アプリなどの1分以内の短い音声が最適です。
手順はシンプルです。音声を一度通して聞き、聞き取れた範囲をノートに書きます。次にスクリプトを確認して答え合わせをし、どこが聞き取れなかったかを分析します。すると、自分が苦手とする音(たとえば /r/ と /l/、母音の短縮など)が分かります。この「気づき」が、リスニング改善の核心です。
ポイントは完璧に書き取ることではなく、なぜ聞き取れなかったかを理解すること。単語を知らないのか、音の連結に慣れていないのか、スピードが速いのか。それぞれ原因が異なります。この分析を繰り返すと、脳が「音から意味を引き出す処理」に慣れ、実際の会話でも内容を追えるようになります。
ステップ③ 「シャドーイング」で英語をリアルタイム処理する
ディクテーションで音を認識できるようになったら、次は「シャドーイング」に進みましょう。これは、聞こえた音声を少し遅れて口に出して真似するトレーニングです。英語を聞きながら同時に再現するため、リスニング力とスピーキング力を同時に鍛えられます。
最初はスピードの遅い教材を使い、聞き取りやすい文を選びます。はじめはスクリプトを見ながら発音し、慣れてきたら文字を見ずに音だけを頼りに真似していきましょう。口が追いつかなくても構いません。重要なのは、音のリズムとイントネーションを体で覚えることです。
実際に筆者が行った練習では、Netflixのドラマのセリフを使って1日15分間シャドーイングを続けました。最初の1週間は何を言っているか分からなかったのに、2週間を過ぎたころから「知っている単語が聞こえる」ように変化しました。そして1か月後には、ネイティブのスピードでも会話の大意をつかめるようになりました。つまり、シャドーイングは英語の音をリアルタイムで処理する力を育てる最強の方法なのです。
第3章 毎日続けられるリスニング習慣の作り方
「短時間×毎日」がリスニング上達の鍵
英語リスニングの上達には、時間よりも「頻度」が重要です。というのは、脳が英語の音を処理する能力は、一度に長時間学習するよりも、毎日少しずつ刺激を与えることで定着するからです。たとえば、1日10分のリスニングを1週間続けるほうが、週末に1時間まとめて聞くよりも効果があります。
人間の脳は、短い間隔で繰り返し同じ刺激を受けると「これは重要な情報だ」と判断して、神経経路を強化します。つまり、英語の音に毎日触れることで、脳がそのリズムや発音を“慣れた音”として処理し始めるのです。特に朝や通勤時間、家事の合間など「ながら時間」に取り入れると無理なく継続できます。
筆者の例では、朝のコーヒータイムにポッドキャストを10分聞く習慣をつけました。最初は何を言っているのか分からなかったものの、3週間ほどで単語のつながりやイントネーションの変化に自然と気づけるようになりました。だからこそ、リスニング練習は“毎日少しずつ”を意識することが何より大切です。
「教材を固定」して反復することが上達への近道
多くの学習者が陥るのが、「いろいろな教材を使いすぎる」ことです。たくさんの音源を聞くのは一見よさそうに思えますが、実際は効果が分散してしまい、リスニング力が伸びにくくなります。なぜなら、脳が“新しい音声”を毎回処理しようとすると負荷がかかり、定着が難しくなるからです。
おすすめは、ひとつの音源を徹底的に使い倒す方法です。たとえば、同じ1分のニュースやドラマのワンシーンを、ディクテーション・シャドーイング・音読のすべてに使います。最初は聞き取れなかった音も、10回・20回と繰り返すうちに自然と聞こえるようになります。これは“耳が育つ”瞬間です。
さらに、同じ教材を繰り返すことで、リスニング中の“予測力”が高まります。話の展開やイントネーションの流れを事前に予想できるようになると、知らない単語が出ても文脈で理解できるようになります。つまり、教材の固定は「聞き取れなかった英語を聞き取れる英語」に変える最短ルートなのです。
モチベーションを保つには「記録」と「小さな達成感」
リスニング学習が続かない最大の理由は、効果を実感しにくいことです。目に見えた進歩がないと、「本当に上達しているのだろうか」と不安になります。そこで効果的なのが「記録をつけること」と「小さな成功体験を積むこと」です。
たとえば、毎日のリスニング時間をアプリやノートに記録するだけでも、「これだけ続けた」という実感が得られます。さらに、1週間ごとに同じ教材を聞いてどれだけ理解できるようになったかをチェックすれば、成長を数字で把握できます。この“見える化”が、継続のモチベーションになります。
また、目標は「映画を字幕なしで理解する」などの大きなものより、「1分の音声を完全に聞き取る」「1日10分を続ける」などの小さな目標に設定しましょう。これなら達成感を得やすく、次の段階に進む意欲が湧きます。つまり、継続は意志ではなく仕組みで作るのがコツです。
第4章 実践でリスニング力を伸ばすおすすめ教材とアプリ
初心者から使えるアプリ型教材「スタディサプリENGLISH」
リスニングを基礎から鍛えたい人に最もおすすめなのが、リクルートが提供する「スタディサプリENGLISH」です。このアプリは、英語の音声を聞いて理解するプロセスを科学的に設計しており、特に初心者が「聞き取れない壁」を乗り越えるのに最適です。
特徴は、短い会話音声を使い、ディクテーションやシャドーイングを同時に練習できる点です。しかも、スクリプトと日本語訳がワンタップで切り替えられるため、自分の弱点をすぐに確認できます。たとえば “How’s it going?” のような日常表現も、音の連結や省略が音声で再現されており、自然な英語のリズムに慣れることができます。
筆者も実際にこのアプリで1日15分の学習を1か月続けたところ、以前は聞き取れなかった映画のセリフが部分的に理解できるようになりました。つまり、スタディサプリは「耳で理解する基礎力」を固めるのに非常に優れた教材です。スキマ時間に取り組める点も社会人にとって大きなメリットでしょう。
実践会話力を磨ける「ネイティブキャンプ」
次におすすめなのが、オンライン英会話の「ネイティブキャンプ」です。リスニングは「相手の話を理解する力」であり、実際の会話でこそ本当の力が試されます。ネイティブキャンプでは世界130カ国以上の講師と24時間いつでもレッスンでき、しかも回数無制限という圧倒的なコスパを誇ります。
特にリスニング強化に有効なのが「カランメソッド」。これは、講師の質問に瞬時に英語で答えるトレーニングで、音の処理スピードを飛躍的に高めます。聞いた音をそのまま口で再現することで、脳が“英語を聞いて理解する”リズムに慣れていきます。最初は大変ですが、続けるうちに耳と口が連動して働くようになります。
また、講師によってスピードやアクセントが異なるため、様々な英語に触れられるのも大きな利点です。映画やニュースで多様な発音に出会っても戸惑わなくなり、実践的なリスニング力が身につきます。自宅で“リアルな英会話環境”を作れることが、このサービスの最大の魅力です。
中上級者に最適な「TED」「YouTube」「Netflix」の活用法
基礎的な聞き取り力がついたら、次のステップは“生の英語”を聞くことです。おすすめは「TED Talks」「YouTube英語チャンネル」「Netflixの英語字幕付きドラマ」です。これらの教材は、ネイティブが自然に話すスピード・発音・イントネーションをリアルに体感できます。
TEDでは発音が明瞭でテーマも幅広いため、ビジネス英語にも役立ちます。YouTubeでは、たとえば “English with Lucy” や “BBC Learning English” のような教育系チャンネルがリスニング練習に最適です。Netflixの場合は、英語字幕をONにして一度視聴し、次に字幕なしで再視聴する方法が効果的です。こうすることで、音と意味の一致を確認できます。
重要なのは「視聴を勉強化しないこと」。楽しい映画や興味のあるテーマを選ぶことで、英語を自然な音として受け入れられるようになります。筆者の場合も、好きな海外ドラマを題材にシャドーイングを続けた結果、2か月でリスニング速度が格段に上がりました。つまり、教材は“好き”で選ぶことが、最強の継続法なのです。
第5章 「聞き取れる英語」に変わる2か月プログラム
第1〜2週:「音の変化」と「発音感覚」を身につける期間
リスニング改善の最初の2週間は、「音を正確に捉える耳づくり」に集中しましょう。この段階では、文法や長文理解よりも、英語特有の音の変化やリズムに慣れることが最優先です。なぜなら、ここで音の土台を作らなければ、その後のリスニング練習がすべて「聞き流し」になってしまうからです。
具体的には、1日15分の「発音模写+オーバーラッピング」を中心に行います。教材は『スタディサプリENGLISH』や『BBC Learning English』など、短い会話が収録されているものを選びましょう。スクリプトを見ながら1文ずつ音を真似し、リエゾン(音のつながり)や弱形を意識します。
この時期は、完璧に発音できなくても構いません。大切なのは「音の消え方」「強弱のリズム」を感じ取ることです。2週間続けると、耳が徐々に英語のスピードに順応し、以前よりも単語の輪郭がはっきり聞こえるようになります。
第3〜5週:「ディクテーション+シャドーイング」で理解力を伸ばす
次の3週間は、「聞き取れた音を意味に結びつける力」を鍛える段階です。この期間で行うのが、ディクテーションとシャドーイングの併用トレーニングです。ディクテーションで音の抜けを確認し、シャドーイングで脳の処理速度を高めます。
まずは1分以内の音声を選び、1回聞いて分かる範囲をノートに書き取ります。その後スクリプトを見て答え合わせをし、どの音を聞き逃したのかを分析しましょう。次に、同じ音声でシャドーイングを3〜5回繰り返します。このとき、発音の細部よりも「テンポと抑揚を真似する」ことを意識してください。
この3週間を経ると、英語を日本語に訳さず理解する感覚が少しずつ身につきます。たとえば以前は「一語ずつ追っていた音声」が、今では「まとまりで理解できる」ようになります。この段階に入ると、英語ニュースや海外YouTubeも聞きやすくなり、実践的なリスニング力が芽生え始めます。
第6〜8週:「実践素材」で“生きた英語耳”を完成させる
最後の3週間は、実際の英語を使った“実践リスニング”の期間です。ここでは、教材を卒業し、Netflix・TED・ポッドキャストなどリアルな英語に触れましょう。目的は、訓練で培ったリスニングスキルを実際のスピードや多様な発音に対応させることです。
おすすめの方法は、好きなドラマや動画を「3段階」で視聴することです。まずは英語字幕をつけて視聴し、次に字幕なしで聞く。最後に再び字幕付きで確認します。この繰り返しにより、音と意味のギャップを徐々に埋めることができます。とくにTEDのように発音が明瞭なスピーチは、リスニング練習に最適です。
この最終フェーズで大切なのは、「完璧を目指さない」ことです。全てを聞き取ろうとすると疲れてしまいますが、7〜8割理解できれば十分です。聞き取れない部分は文脈で推測し、内容を楽しみながら聞き続けましょう。2か月を終えるころには、英語の音が以前よりも自然に耳に入り、ニュースや映画を「理解しながら聞ける」状態に近づいているはずです。
まとめ:リスニングは才能ではなく、正しい手順で伸びる
英語リスニングが聞き取れない原因の多くは、「音の変化を知らない」「脳の処理順序が違う」「練習の順番を間違えている」というシンプルな理由にあります。つまり、センスや才能ではなく、正しい方法を知るかどうかで結果が変わるのです。
まずは、英語の音そのものを理解することから始めましょう。発音模写やオーバーラッピングで音の構造を体に染み込ませ、ディクテーションで弱点を明確にし、シャドーイングで脳を英語のスピードに慣らしていく。この3ステップを繰り返せば、確実にリスニング力は上がります。
さらに、学習を習慣化することも欠かせません。1日10分でも毎日続けることで、英語のリズムが脳に定着します。教材はひとつに絞り、何度も反復するのがコツです。やがて同じ音声を聞いたとき、「あ、今の単語聞こえた」と実感できる瞬間が訪れるでしょう。
最後に強調したいのは、リスニングは“理解するトレーニング”であるということです。文字を追う勉強ではなく、耳から意味を掴む力を育てるもの。焦らず、音を楽しみながら続けてください。あなたの耳は、必ず英語を聞き取れる耳に変わります。2か月後には、これまで聞き取れなかった会話が自然に理解できるようになっているはずです。
今日から始められることはたったひとつ──毎日英語の音を聞くこと。それが、リスニング上達のすべての出発点です。