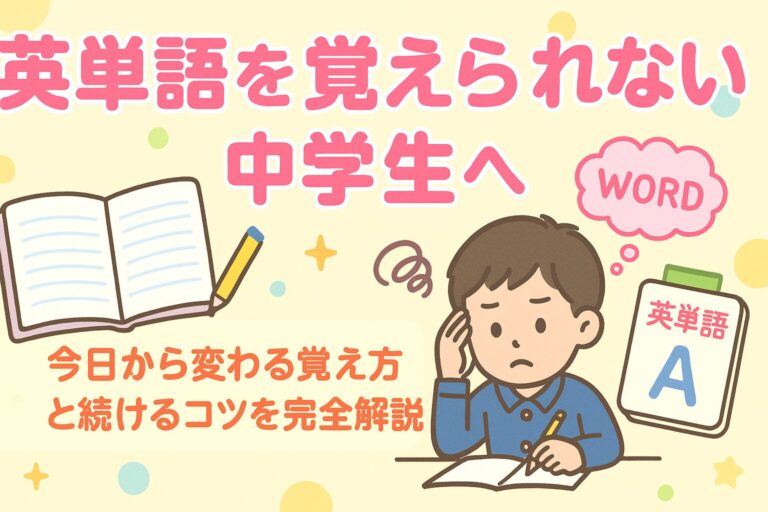「何度書いても英単語が覚えられない…」「テスト前に頑張ってもすぐ忘れてしまう…」そんな悩みを抱える中学生はとても多いです。単語帳を何周しても記憶が定着せず、時間ばかりが過ぎていく。この現象には、明確な理由があります。単に「暗記が苦手」なのではなく、英語の学び方そのものに原因があるのです。
この記事では、英単語をどうしても覚えられない中学生が「確実に記憶できるようになる方法」を、最新の学習理論と教育現場の実例をもとに解説します。さらに、フォニックス・語源・発音・色分けなど、実際に成果の出た学習法も紹介します。どんな生徒でも、「英単語が苦手」から抜け出せるヒントが必ず見つかるはずです。
コンテンツ
なぜ中学生は英単語を覚えられないのか
原因1:ローマ字読みの癖が抜けない
多くの中学生が英単語を正しく覚えられない最大の理由は、「ローマ字読みの癖」が抜けないことにあります。日本の小学校では、英語よりも先にローマ字を学びます。これは国語の授業の一部として扱われ、アルファベットを“日本語を表す記号”として覚えてしまうのです。そのため、「英語も日本語の書き方の一種」と誤って認識したまま英語学習に入ってしまう生徒が多くいます。
たとえば、“through”という単語を「トゥロウ」と読んでしまったり、“minute”を「ミヌテ」と読むような誤りは、まさにローマ字読みの延長です。これは中学生本人の努力不足ではなく、学習順序の問題によるものです。つまり、英語を「音のある言語」としてではなく、「文字の並び」として覚えようとしてしまっているのです。その結果、発音と意味が結びつかず、どれだけ書いても記憶に残りません。
このような場合、まず必要なのは「英語は日本語とはまったく別の言語である」という認識を持つことです。アルファベットは“日本語の表記”ではなく、“英語の音を表す記号”であると理解し直すだけでも、暗記の定着率は大きく変わります。発音と綴りを同時に学ぶ「フォニックス」を活用すると、英語の音の仕組みを自然に理解でき、ローマ字読みの癖が徐々に消えていきます。
原因2:音と綴りを別々に覚えている
もう一つの大きな原因は、「音と綴り(スペル)を別々に覚えている」ことです。多くの生徒は、単語帳の日本語訳を見てひたすら書き写す学習を繰り返しています。しかし、これは脳の記憶構造に反しています。人間の脳は、「音」と「意味」と「イメージ」が結びつくことで長期記憶を形成します。逆に、文字情報だけを機械的に覚えようとすると、短期記憶にしか残らず、翌日には忘れてしまうのです。
たとえば、“thank”という単語を「サンク」と書いて覚えた場合、実際に“th”の発音を理解していなければ、正しい音を聞いたときに結びつかなくなります。結果として、リスニングにも弱くなり、「知っている単語なのに聞き取れない」という現象が起こります。これは、中学生に特に多く見られるパターンです。
そのため、単語を覚えるときは「綴りと発音を必ずセット」で覚えることが重要です。英単語帳やアプリの音声を必ず再生し、発音をまねしながら書く。この小さな習慣が記憶定着のカギです。さらに、声に出して覚えることで、視覚・聴覚・運動感覚の3つが同時に刺激され、記憶が長期化します。これこそが、何百回書くよりも効果のある「科学的な覚え方」なのです。
原因3:単語を「日本語の別名」として覚えている
中学生が単語を覚えにくいもう一つの理由は、「英単語=日本語の別名」として記憶してしまうことです。たとえば、「apple=りんご」「dog=いぬ」と対応させるだけの暗記は、一見シンプルですが非常に脆い記憶です。なぜなら、その単語を“概念”としてではなく、“置き換え語”としてしか認識していないからです。
たとえば、“run”という単語を「走る」とだけ覚えていると、“run a company(会社を経営する)”や“run out(使い果たす)”といった表現に出会ったときに理解できません。つまり、「単語を日本語で変換して覚える」学習では、応用力が育たないのです。
英語を得意にする生徒ほど、単語を“イメージ”や“状況”で覚えています。たとえば、“rain”を聞いたら「傘をさしている情景」が浮かぶように、“sleep”を見たら「ベッドで眠る姿」が思い浮かぶようにする。このようにイメージで結びつけることで、単語の意味が頭の中で自然に定着します。
英語を英語のまま理解する「イメージ記憶」を意識すると、長文読解でもいちいち日本語に訳す必要がなくなります。その結果、読むスピードが上がり、英語が「わかる」感覚に変わっていくのです。
中学生が英単語を覚えられない理由は、暗記力の問題ではありません。音・意味・イメージの三つが結びついていないことが根本原因です。この仕組みを理解することが、次のステップ「効果的な覚え方」への第一歩となります。
英単語を確実に覚えるための5つのステップ
ステップ1:フォニックスで「音と文字のルール」を身につける
英単語を覚えるうえで、もっとも効果的な第一歩が「フォニックス学習」です。フォニックスとは、英語の文字と発音の関係を学ぶ方法で、英語圏の子どもたちはこのルールを通して読み書きを習得します。日本の学校ではあまり詳しく扱われませんが、実はこの基礎がないまま英単語を覚えようとすると、まるで暗号を解くような作業になってしまうのです。
たとえば「a」は「エイ」と読むときもあれば、「ア」や「エァ」と読むときもあります。この音の変化には明確な規則があり、それを理解することで、初めて見る単語でも発音や綴りを推測できるようになります。代表的なのが「マジックEの法則」で、たとえば「cap」と「cape」では、最後のEが前の母音を「エイ」と伸ばす働きをします。このような規則を知っておくと、英単語の暗記が何倍も速くなるのです。
フォニックスはYouTubeの子ども向け動画や市販の教材でも学べます。中学生でも理解しやすいものが多く、発音練習にも最適です。フォニックスを取り入れることで、単語の「音」と「綴り」が頭の中で一つにつながり、書く・読む・聞く・話すのすべてがスムーズになります。
ステップ2:音読とシャドーイングで「耳と口を連動させる」
フォニックスで音のルールを理解したら、次は「音読」と「シャドーイング」を組み合わせて練習します。音読はただ声に出すだけではなく、目で見た文字を耳で確認しながら声に出す学習法です。さらに、シャドーイングとは、英語音声を聞きながら少し遅れてまねして発音する方法で、リスニングとスピーキングを同時に鍛えられます。
この方法を使うと、英単語の音と意味が自然に結びつき、記憶の定着率が一気に高まります。たとえば、“beautiful”という単語を10回書くより、発音をまねして5回声に出す方が、長期記憶として残りやすいことが科学的にも証明されています。音と口の動きの感覚が加わることで、脳の複数の領域が同時に働き、単語を「体で覚える」状態になるのです。
おすすめは、1日10分でもいいので、英単語帳の音声を再生しながら発音練習をすることです。特に「r」「l」「th」など日本語にない音は、口の形と舌の位置を意識して練習すると効果的です。最初は違和感があっても、1週間ほど続ければ確実に発音が安定し、リスニング力も向上します。
ステップ3:語源で意味のまとまりをつかむ
英単語を丸暗記するのではなく、「語源」から理解することも非常に効果的です。英語の多くの単語は、ラテン語やギリシャ語をもとに作られており、語源を知ることで複数の単語を一度に覚えられるようになります。
たとえば、“tele”は「遠く」という意味の語源です。“telephone(電話)”“television(テレビ)”“teleport(瞬間移動)”など、すべて「遠くに関係する」言葉としてグループ化できます。つまり、「tele=遠く」と覚えておけば、初めて見た単語でも意味を推測できるのです。
また、“port”は「運ぶ」という意味があり、“import(輸入する)”“export(輸出する)”“transport(運搬する)”のように派生語をまとめて理解できます。語源暗記は単語数を効率的に増やすだけでなく、文章を読んだときの理解スピードも飛躍的に上がります。
中学生向けには、語源をイラストや色分けで説明している単語帳もおすすめです。関連語をグループで覚えると、単語が「ばらばらの点」から「意味でつながる線」へと変わります。
ステップ4:自己テストで記憶を「思い出す」練習をする
「覚える」ことよりも大切なのは、「思い出す」練習です。脳は、何度も情報を思い出すことで記憶を固定化します。この仕組みを利用したのが「自己テスト法」で、書いたり声に出したりする代わりに、自分で小テストを繰り返す学習です。
たとえば、5単語ずつ覚えて、すぐに日本語→英語で書けるかをテストします。1つでも間違えたら、そのグループを再テスト。翌日にもう一度同じテストを行うと、記憶の定着率が倍増します。これは「エビングハウスの忘却曲線」に基づいた方法で、翌日に復習するタイミングがもっとも効率的であることが証明されています。
また、アプリを使えば自動でテスト機能を実施できるものもあります。特に「ターゲット1800」や「英単語暗記カード」などは、発音付きでチェックできるため、中学生にも最適です。重要なのは、完璧に覚えるより「思い出す回数を増やす」ことです。これを習慣化するだけで、暗記のストレスがぐっと減ります。
ステップ5:単語を「使って」覚える
最後のステップは、「覚えた単語を実際に使う」ことです。単語を使わないまま放置すると、せっかく覚えた知識も数日で薄れてしまいます。英語は言葉である以上、使うことで初めて脳に定着します。
おすすめは、「例文暗記」と「日記英作文」です。たとえば、“I have a cat.”を覚えたら、“I have a book.”“I have a dream.”のように自分の生活に合わせて応用してみましょう。自分の感情や日常と結びつけて使うことで、単語が“自分の言葉”として記憶に残ります。
また、SNSやノートに英語の一言メモを残すのも効果的です。「Today was fun!」「I studied English today!」など、短いフレーズでも構いません。こうした小さなアウトプットの積み重ねが、最も強い記憶の固定化を促します。
以上の5ステップを実践することで、単語学習は「退屈な暗記」から「意味のある理解」へと変わります。重要なのは、「書く」よりも「聞く・話す・使う」。それが、英単語を確実に覚える最短ルートです。
中学生におすすめの英単語勉強法と教材
方法1:例文ごと覚えて「使える単語」にする
英単語を単体で覚えるよりも、例文とセットで覚える方が圧倒的に効果的です。理由は簡単で、人間の脳は「文脈のある情報」を長く記憶に残すからです。たとえば、“This is a pen.”という文を丸ごと覚えておけば、“This is a dog.”や“This is a car.”と応用でき、単語が「使える知識」に変わります。
また、例文暗記には「文法力を一緒に鍛えられる」というメリットもあります。単語帳にある短いフレーズを声に出して繰り返すだけでも、英文の構造が自然に身につきます。中学生のうちは、難しい文章よりも「短く・リズムよく・繰り返し言える」例文を選ぶのがコツです。
おすすめは、『高校入試でる順ターゲット 中学英単語1800』のような、例文付き単語帳です。この教材は、英単語を文中でどう使うかを一緒に学べる構成になっており、リスニング用の音声も無料でダウンロードできます。耳から覚える学習にも最適です。
方法2:アプリを活用してスキマ時間を学習時間に変える
現代の中学生にとって、スマートフォンを利用した英語学習は非常に有効です。アプリを使えば、通学中や休み時間などの短時間でも効率的に単語を復習できます。特に、アプリの強みは「自動で復習タイミングを管理してくれる」点にあります。覚えた単語を忘れかけた頃に出題してくれるため、記憶の定着が飛躍的に向上します。
代表的なアプリには「mikan」や「ターゲットの友」などがあります。これらは高校入試対応の英単語帳と連動しており、音声やテスト機能も充実しています。また、発音練習ができる「ELSA Speak」などのアプリを組み合わせれば、スピーキング力の強化にもつながります。
ただし、アプリ学習の注意点は「受け身にならないこと」です。画面を眺めるだけでは意味がありません。必ず声に出して発音し、指でタップして答えるなど、体を動かすようにすると効果が倍増します。スキマ時間の5分でも、集中して繰り返すことで確かな成果が出ます。
方法3:色と感情で記憶を強化する「色分け学習法」
人間の記憶は、視覚情報と感情が結びついたときに長く残ります。そこで有効なのが「色分け学習法」です。単語の意味や感情に応じて、ノートや単語カードに色をつけておくと、記憶の定着が格段に高まります。
たとえば、「ポジティブな意味の単語」は青、「ネガティブな意味の単語」は赤、「動作を表す単語」は緑、「感情を表す単語」は黄色、といったように分類します。特に青と赤は脳への印象が強く、色の違いで記憶の整理がしやすくなるのです。
また、単語に対して「感情」を結びつけることも効果的です。たとえば、“excited”なら「ワクワクする」、 “tired”なら「ぐったりする」など、気持ちを思い浮かべながら覚えると、単語が生きたイメージとして残ります。脳は「感情を伴った記憶」を優先的に保存するため、この方法は受験勉強にも非常に有効です。
方法4:五感を使って「英単語を体で覚える」
記憶を定着させるには、視覚・聴覚・運動感覚の3つを同時に使うのがポイントです。つまり、書くだけでなく、見て、聞いて、発音して、指や口を動かすことが重要です。これを「マルチモーダル学習」と呼びます。
たとえば、英単語を「聞きながら書く」練習をすれば、耳と手の動きが連動し、記憶がより強固になります。さらに、単語を声に出しながらリズムよく覚えると、リズム記憶が働いてスムーズに口から出てくるようになります。こうした方法は、外国語学習における定番の科学的手法です。
また、発音練習のときは鏡を使って口の形を確認するのも効果的です。自分の口の動きを視覚で捉えることで、筋肉の動きが定着しやすくなります。特に「th」や「r」「l」などの発音は、口の位置と舌の使い方を意識しないと習得が難しいため、鏡練習は欠かせません。
方法5:学びを習慣化する「ミニ英語ルーティン」を作る
どんなに良い方法でも、続かなければ意味がありません。英単語学習を習慣化するためには、「ミニルーティン」を作ることが大切です。これは1日10〜15分の短時間学習を、毎日同じタイミングで行う習慣のことです。
たとえば、「朝起きて10分アプリを使う」「夜寝る前に5単語音読する」といった小さなルールを設定します。重要なのは、無理のない範囲で継続することです。脳は「毎日同じ行動」を覚えるようにできているため、数週間で自然と習慣になります。
また、勉強の進捗を「見える化」するのもおすすめです。単語カードにチェックマークを入れる、アプリの学習記録を確認するなど、小さな達成感を積み重ねることでモチベーションが続きます。英語が得意な中学生の多くは、この「コツコツ習慣」を確立しているのです。
このように、英単語学習には「方法」よりも「仕組み」が大切です。自分が続けやすい形で日常に取り入れれば、覚えられない単語は確実に減っていきます。
英単語が苦手な中学生が陥りやすい勘違い
勘違い1:「書けば覚えられる」と思い込んでいる
多くの中学生がやってしまうのが、「とにかく書けば覚えられる」という勘違いです。確かに「手を動かして覚える」という方法は昔から定番ですが、脳科学的には「書く=記憶する」ではありません。むしろ、何も考えずに同じ単語を何十回も書く作業は、脳が「単なる動作」として処理してしまい、記憶に残りにくいのです。
たとえば、“beautiful”を30回書いても、翌日には綴りを忘れてしまうことがあります。これは、書く行為に「思考」や「理解」が伴っていないからです。記憶を定着させるには、「どういう意味だっけ?」「どんな場面で使うんだっけ?」と、頭を使いながら書くことが大切です。
つまり、「量より質」。10回書くより、1回声に出して発音しながら意味をイメージした方が効果的です。ノートに書くことを「確認作業」と捉え、覚えるプロセスは音や映像など多感覚で行うと、記憶の定着が何倍にもなります。
勘違い2:「自分は記憶力が悪い」と思い込む
「どうせ自分は記憶力が悪いから」と諦めてしまう中学生も少なくありません。しかし、実際に英単語が覚えられないのは、記憶力のせいではなく「覚え方のパターン」が合っていないだけです。脳のタイプには個人差があり、視覚型・聴覚型・体感型など、それぞれ得意な記憶方法が存在します。
たとえば、音で覚えるのが得意な子は、音読やリスニング中心の学習が向いています。逆に、文字を見るのが得意な子は、色分けやカードでの整理が効果的です。つまり、「覚え方が合っていない」だけであって、記憶力そのものが悪いわけではありません。
また、英単語を“日本語で覚えようとする”こと自体が記憶を妨げている場合もあります。日本語変換を介さず、イメージや状況で覚えるようにすると、理解スピードも記憶力も飛躍的に上がります。自分に合った覚え方を見つけることこそ、英語が得意になる第一歩です。
勘違い3:「英語のセンスがない」と決めつけている
「英語のセンスがないから仕方ない」と思い込む生徒もいますが、英語のセンスは生まれつきの才能ではなく「慣れ」です。英語を多く聞き、多く使い、多く触れるうちに自然と身につく能力です。たとえば、英語を読む機会が多い子は、自然と文のリズムや語感をつかめるようになります。これは「センス」ではなく「経験の差」です。
たとえば、好きなアニメの英語版を観たり、洋楽の歌詞を調べたりするだけでも、語感は鍛えられます。英語を日常の中に取り入れることで、「苦手意識」は自然と薄れていきます。ポイントは、「英語=勉強」ではなく「英語=ツール」として触れること。意味を理解しようとせず、まずは「音やリズムを楽しむ」ことから始めてみましょう。
また、学校の成績やテストの点数で英語の才能を判断するのも間違いです。英語は知識だけではなく「慣れ」と「継続」で伸びる教科です。つまり、始めるのが遅くても、正しい方法を続ければ必ず上達します。英単語が覚えられない状態も、学習法を変えるだけで劇的に改善できるのです。
このように、英単語が苦手な中学生が抱く多くの「思い込み」は、実際にはただの誤解です。大切なのは、「自分にはできる方法を見つけること」と「小さな成功体験を積み重ねること」。英語は努力を続けた人が、最終的に一番伸びる科目です。
英単語暗記がうまくいく中学生の共通点
共通点1:発音と意味を「同時に」覚えている
英単語をスムーズに覚える中学生の多くは、必ず「発音」と「意味」を同時にセットで覚えています。単語を文字だけで見て覚えるのではなく、音声を聞きながらリズムで覚えていくのです。たとえば、“apple”を「アップル」と日本語で読んでしまうのではなく、“æpl”という英語の音を口に出して覚えています。
こうした生徒たちは、単語帳の音声を必ず再生し、口の動きをまねしながらリピートしています。この習慣により、リスニング力・スピーキング力・暗記力の三つが同時に伸びるのです。つまり、発音と意味を一緒に覚えることは、英単語を「頭で覚える」から「体で覚える」に変えるスイッチになります。
また、音声と一緒にリズムを意識すると記憶の定着がさらに良くなります。英単語には一定のアクセントやリズムがあるため、メロディーのように繰り返すことで自然に記憶が残るのです。これが、「発音と意味を同時に覚える」生徒が暗記上手な理由です。
共通点2:「毎日少しずつ」を継続している
英単語を覚えるのが上手な中学生は、1日に100語を詰め込むような勉強はしていません。代わりに「毎日少しずつ」を習慣化しています。たとえば、1日10語ずつ覚えれば、1か月で300語、3か月で900語になります。これは高校入試の英単語数に匹敵する量です。
このように「コツコツ積み上げるタイプ」の生徒は、忘れにくく、復習もしやすいのが特徴です。脳は短時間・高頻度の繰り返しに最も反応します。長時間の詰め込み学習よりも、1日10分を毎日続ける方がはるかに効果的なのです。
さらに、覚えた単語を「寝る前に1分だけ復習する」習慣を持つ生徒は、翌日の定着率が劇的に上がります。睡眠中に記憶が整理されるため、夜の復習は非常に効率的です。つまり、「毎日少しずつ」「寝る前に確認」——この2つのリズムが成功する中学生の共通点です。
共通点3:間違いを「失敗」ではなく「発見」と捉えている
英単語暗記が得意な中学生は、「間違えること」を恐れません。むしろ、「間違えた=覚え直すチャンス」と考えています。英語の学習においては、間違いの数こそが上達の証です。最初から完璧を目指すよりも、何度もテストをして「自分がまだ覚えていない単語」を発見する方が早いのです。
たとえば、自己テストをしたときに5語中3語しか正解できなかった場合、2語を「もう一度強化するリスト」に入れます。この「弱点リスト」を繰り返し復習していくうちに、次第に覚えていない単語が減り、すべての単語が安定して記憶されるようになります。
また、「失敗を恐れない生徒」は、自分の発音や英作文にも積極的です。間違えるたびに正しい形を学び、脳の中で英語の構造を強化していきます。これは心理学的にも「エラー学習」と呼ばれる効果で、失敗を通して記憶が深まるというものです。つまり、失敗を前向きに受け止める姿勢こそが、暗記成功の最短ルートなのです。
共通点4:「使う目的」が明確になっている
英単語を覚えるのが得意な生徒ほど、「なぜ覚えるのか」が明確です。たとえば、「英検に合格したい」「海外旅行で会話したい」「好きな映画を字幕なしで観たい」など、具体的な目標を持っています。目的があると、単語学習が“作業”ではなく“手段”になります。
目的を意識すると、単語一つひとつの意味に感情が宿り、記憶が深まります。たとえば、“dream”という単語を「夢」と覚えるより、「将来の夢」と自分の人生と結びつけて覚える方が、はるかに印象に残ります。つまり、「自分に関係ある単語」ほど忘れにくいのです。
さらに、目的を紙に書き出して机の前に貼っておくと、やる気の維持にも効果的です。人間の脳は「視覚的に目に入る情報」を潜在意識に刻みやすいため、モチベーションが下がったときにも自然と勉強を続けられます。
共通点5:「楽しさ」を見つけている
最後に、英単語が定着する生徒の一番の特徴は「楽しさを見つけている」ことです。英語を“勉強”ではなく“コミュニケーションの道具”として楽しんでいます。たとえば、好きな映画を英語字幕で観る、海外のYouTuberの動画をまねしてみる、英語の歌を口ずさむなど、遊びながら学んでいるのです。
楽しさを感じると、脳内で「ドーパミン」という神経伝達物質が分泌され、集中力と記憶力が大幅に向上します。これは科学的にも証明された効果で、ワクワクしながら学ぶと、自然と単語が頭に残ります。つまり、「楽しく学ぶこと」こそが最強の暗記法なのです。
英単語学習において重要なのは、「自分が成長している実感」を持つことです。少しずつ単語が増えていく感覚を楽しめば、英語が苦手だった中学生でも、いつの間にか得意科目に変わっていきます。
英単語がスラスラ覚えられる勉強スケジュール例
スケジュール1:1日15分で続ける「朝・夜リズム法」
英単語を無理なく定着させるには、「朝」と「夜」に短時間の学習を取り入れるのが最も効果的です。朝は脳がクリアな状態で記憶力が高く、夜は学んだことを睡眠中に整理する時間があるため、記憶の定着が格段に上がります。
具体的なスケジュールとしては、朝起きてすぐの10分で新しい単語を5~10個覚え、夜寝る前の5分でその日の復習を行うだけです。朝に「インプット」、夜に「リマインド(再確認)」という流れを作ると、脳が情報を短期記憶から長期記憶に移す準備をします。
また、朝の勉強では必ず声に出して発音することを意識しましょう。音声を使うと、単語のリズムが体にしみ込み、思い出しやすくなります。夜は「聞くだけ復習」でも構いません。寝る直前に音声を聞くと、脳内で英語のリズムが繰り返され、翌朝の記憶定着がより強化されます。
スケジュール2:週ごとにテーマを決めて学ぶ「週単位集中法」
英単語をランダムに覚えるより、「テーマ別」にまとめて覚える方が効率的です。なぜなら、人間の脳は「関連する情報」をまとめて保存する性質を持っているからです。たとえば、「学校」「食べ物」「感情」「動作」など、1週間ごとにテーマを変えると、記憶が整理されやすくなります。
月曜日から金曜日までは新しい単語を覚える日、土曜日に総復習、日曜日は“テストデー”というスケジュールがおすすめです。たとえば、1日10語×5日で50語を学び、土曜にまとめて音読・発音練習、日曜に自己テストを行う。これを4週間続けるだけで、1か月で200語以上を定着させることができます。
この方法は、忘却曲線に沿った理想的な復習サイクルでもあります。覚えた単語を「翌日」「3日後」「1週間後」と少しずつ間隔を広げながら復習すると、記憶が安定して長持ちします。カレンダーに学習テーマを書き込んでおくと、視覚的にも管理しやすく、習慣化がスムーズになります。
スケジュール3:テスト対策に強い「3段階暗記法」
定期テストや入試に備える中学生には、「3段階暗記法」が非常に効果的です。この方法は「①覚える→②確認する→③使う」の流れで記憶を強化していくステップ構成です。
まず①覚える段階では、単語帳やアプリを使って意味と発音を同時に学びます。このとき、5~10語単位で区切り、無理のない範囲に絞ることがポイントです。次に②確認する段階では、翌日または翌週に自己テストを行い、記憶の抜けをチェックします。間違えた単語は「要復習リスト」にまとめておきましょう。
最後に③使う段階では、実際に英作文や会話練習に取り入れます。たとえば、“I like music.”や“I want to visit Tokyo.”など、シンプルな文に覚えた単語を入れて声に出すことで、知識が「使える力」に変わります。書いて終わりではなく、使って覚える。この「アウトプット学習」が記憶を長期化させる最大の鍵です。
スケジュール4:苦手単語を減らす「復習ループ法」
どんなに頑張っても、なかなか覚えられない単語は誰にでもあります。そこで有効なのが「復習ループ法」です。これは、覚えられなかった単語を3日・7日・14日後に再確認する方法で、忘れやすい単語を自然と定着させる仕組みです。
具体的には、単語帳のページにマークをつけておき、「1回目で覚えられなかった単語」は3日後、「2回目で間違えた単語」は7日後、「3回目で不安な単語」は2週間後に再テストします。このサイクルを繰り返すと、苦手単語も確実に記憶に残ります。
また、苦手単語だけを集めた「ミニノート」を作るのもおすすめです。苦手単語は短期間で繰り返し触れるほど定着が早くなります。覚えにくい単語を「特別扱い」してあげる感覚で、重点的に見直していきましょう。
スケジュール5:勉強が続く「ごほうび式ルーティン」
勉強を長く続けるためには、「ごほうび」を設定するのが効果的です。心理学では、小さな報酬が習慣化を強化すると言われています。たとえば、「1週間連続で単語練習ができたら好きなスイーツを食べる」「30分勉強したら10分YouTubeを見ていい」など、自分に合ったルールを作りましょう。
重要なのは、達成できる範囲の目標を設定することです。大きな目標だけだと続かないため、日ごとの「小さな成功」を積み重ねていきます。こうすることで、英語の勉強が「義務」から「楽しみ」に変わり、自然と続けられるようになります。
勉強の習慣化に成功した中学生の多くは、このように「学習+報酬」のサイクルを上手に使っています。自分の努力をしっかり褒めてあげることが、次の一歩を踏み出すエネルギーになるのです。
まとめ:英単語を覚えられない中学生が今日から変わる方法
英単語をなかなか覚えられないと感じている中学生は決して少なくありません。ですが、覚えられない原因は「自分の能力の問題」ではなく、「覚え方が合っていない」だけです。正しい学び方に切り替えれば、どんな生徒でも必ず覚えられるようになります。
まず理解しておきたいのは、英単語の記憶には「音」「イメージ」「使う経験」の3つが必要だということです。文字だけで覚えようとするのではなく、音声を聞き、発音し、使うことで脳が自然に記憶を固定します。フォニックスで音と綴りの関係を理解し、発音と意味をセットで学ぶことが何よりの近道です。
次に大切なのは「継続」です。1日10分でもいいので、毎日英単語に触れる習慣を作りましょう。朝と夜の2回の短時間学習、または週ごとにテーマを決めた集中法など、自分に合ったリズムを見つけることが成功のカギです。無理をせず、小さな達成を積み重ねていくことが、結果的に大きな成果につながります。
さらに、覚えた単語は「使う」ことで定着します。英作文や日記、SNSなどで実際に英単語を使ってみましょう。たとえば、学んだ単語を使って「今日の出来事」を英語で書くと、知識が“自分の言葉”として残ります。単語を「知っている」から「使える」に変えることで、英語の理解力も飛躍的に伸びます。
そして、間違いを恐れないこと。英語は失敗を繰り返しながら上達する教科です。間違えた分だけ記憶は深くなります。テストで間違えた単語は「チャンス」として受け止め、復習リストに入れて繰り返しましょう。それこそが、本当に身につく学習サイクルです。
最後に、英語学習を「楽しむ」ことを忘れないでください。洋楽を聴く、映画を英語字幕で観る、海外の動画を見るなど、英語を身近に感じる時間を増やしましょう。「楽しい」と思える学習は、努力よりもはるかに長く続きます。英語は世界中の人とつながるための“ツール”です。今日からその第一歩を踏み出しましょう。
英単語が覚えられない中学生でも、正しい方法と少しの工夫で必ず変われます。あなたの努力は、必ず結果につながります。今から10分、今日から始めてみましょう。きっと数か月後、「英単語が得意になった自分」に出会えるはずです。