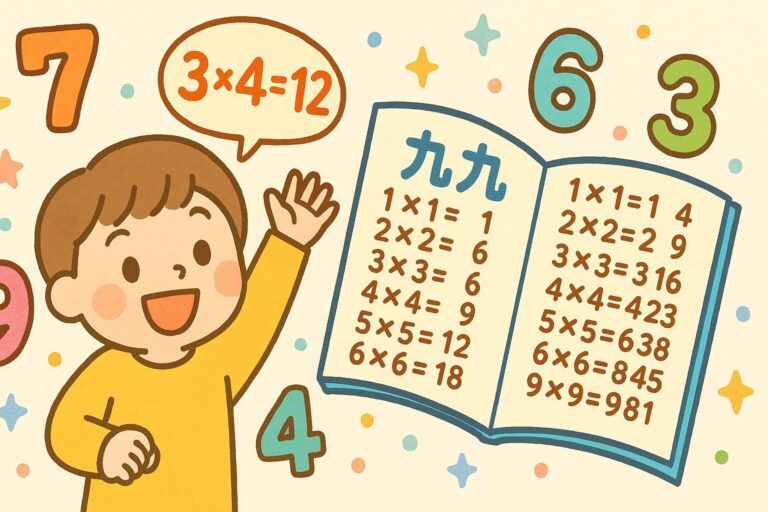コンテンツ
九九が覚えられない子どもの特徴とよくある悩み
九九の暗記に苦手意識を持つ子どもの共通点
九九をスムーズに覚えられない子どもには、いくつかの共通した特徴があります。 たとえば、「同じことを繰り返すのが嫌い」「音で覚えるのが苦手」「集中力が続かない」といった傾向です。
特にADHDやグレーゾーンの子どもは、短期記憶やワーキングメモリに負荷がかかる九九のような反復的な学習が難しく、すぐに飽きてしまうこともあります。 また、リズムに乗りづらい「6の段」「7の段」でつまずくことが多く、途中で投げ出してしまうケースも少なくありません。
九九の習得が遅れても、それは能力の問題ではなく、「学び方のスタイルが合っていない」ことが原因であることが多いのです。 そのため、子ども自身の特性に合った覚え方を見つけることが、最初のステップとなります。
親が感じやすいプレッシャーと不安
「うちの子だけ九九ができないのでは?」と感じる親御さんも多く、家庭学習の時間にイライラしてしまうこともあるでしょう。
しかし、九九の習得が遅れている子は決して少数派ではありません。 小学校2年生という年齢では、まだ記憶力も発達の途中であり、「何度やっても覚えられない」という状況はよくあることです。
大切なのは、「できないこと」ではなく「どうすればできるようになるか」に目を向けることです。 焦らず、子どものペースに合わせたアプローチを心がけましょう。
間違ったアプローチが学習意欲を削ぐことも
九九を「ただ暗記させよう」とするだけでは、子どもは学習そのものに抵抗感を持つようになります。 特に、意味がわからないまま繰り返し唱えさせられると、「つまらない」「やりたくない」と感じ、算数全体に苦手意識が広がるリスクがあります。
また、親の焦りや過度な期待がプレッシャーになり、「九九ができない=ダメな子」という誤った自己評価につながる可能性もあります。 その結果、学びへのモチベーションが低下し、ますます覚えられなくなるという悪循環に陥るのです。
九九の定着を目指すには、まずは子どもの特性を理解し、楽しみながら学べる環境づくりが重要です。 次の見出しでは、子どもの認知スタイル別に効果的な覚え方を紹介します。
「継次処理タイプ」の子に合った九九の覚え方
継次処理スタイルとは?特徴と学習傾向
継次処理タイプの子どもは、「順序立てて物事を理解すること」が得意です。 つまり、情報を一つずつ順番に処理して、段階的に全体を把握するタイプです。
このタイプは、音声情報に強く、「聞いて覚える」「唱えて覚える」といった方法が効果的です。 九九の学習においても、1の段から9の段へと順番に、音声を中心とした繰り返し練習をすることで習得しやすくなります。
反対に、視覚的な情報を同時に処理するのが苦手な場合もあり、九九表を目で追っても頭に入りにくい傾向があります。 したがって、耳からのアプローチを中心に学習環境を整えることがポイントです。
「音読」と「語呂合わせ」を活用した記憶法
継次処理タイプの子には、まず「耳で聞く」→「声に出して読む」→「テンポよく唱える」のステップで九九を学ばせると効果的です。 特におすすめなのが、九九の式と読み方が書かれたカードを使った音読練習です。
たとえば、「しちさんにじゅういち」と声に出して読んだあと、「しちが3こで21になる」というように言葉に置き換えて言わせると、数のイメージが定着しやすくなります。 さらに、「九九のうた」や「九九ラップ」などを使うと、リズムとメロディが記憶を助けてくれます。
YouTubeやCD教材などを利用して、好きな音楽にのせて覚える方法もおすすめです。 音による記憶は反復によって強化されるため、日常生活の中で繰り返し耳にする環境を作るとよいでしょう。
意味の理解より「音としての記憶」を優先する
九九の意味(かけ算の概念)を理解しないまま暗唱できるようになってしまうことに不安を覚える方もいますが、継次処理タイプの子にとっては「まず音として覚える」ことのほうが先です。
最初から意味を教え込もうとすると、かえって混乱することもあるため、最初は「唱える→反復する→音で覚える」というプロセスを重視してください。 九九のパターンやリズムに慣れてきたら、「3が4こで12」などの語彙表現に少しずつ移行していくと理解が深まります。
さらに、身の回りの具体例を使って式の意味を説明するのも効果的です。 「3つずつ並んだリンゴが4列あると全部で何個?」といった形で、実際のイメージに結びつけると理解が進みます。
「同時処理タイプ」の子に合った九九の覚え方
同時処理スタイルとは?特徴と学習傾向
同時処理タイプの子どもは、情報を「全体として捉える」のが得意です。 複数の情報を同時に関連付けて理解する力が強く、視覚情報や空間的な配置、図や表からの学習に向いています。
このタイプの子にとっては、順番に唱えるだけの九九学習では頭に入りにくく、単調な繰り返しにストレスを感じやすい傾向があります。 そのため、九九の「構造」や「法則」を視覚的に捉えられるような工夫が必要です。
また、九九表のように全体を俯瞰して見られる教材や、図解、パターンを使った学習に強みを発揮します。 一つひとつを順番に覚えるのではなく、「どの位置にどの答えがあるか」という“空間記憶”を活かすのが鍵です。
九九表や絵カードを使った視覚的アプローチ
同時処理タイプの子には、九九表を学習の起点にする方法が有効です。 まずは、九九表の中にどんな法則があるかを一緒に観察してみましょう。
「横の列は同じ数ずつ増えている」「斜めに見ると同じ数になる」など、パターンや規則性に気づかせることで、九九に対する興味と理解が深まります。 さらに、色分けされたカードやシールを使って「覚えたい部分」にマークを付けると、視覚的な記憶として定着しやすくなります。
絵カードも非常に有効です。 たとえば、「リンゴが5個入った箱が4つある」という絵を見せて「5×4=20」と導き、九九表の該当位置を一緒に指差すことで、イメージと式を関連付けることができます。
空間把握と反復で「場所ごとに答えを覚える」
九九表を使った学習では、「○段の△はどこにあるか」を何度も確認させることで、記憶の中に九九表そのものの地図をつくるようなイメージで学習が進みます。 これは、視覚と空間の記憶が得意な同時処理タイプの子にとって、非常に効果的なアプローチです。
カードを使って九九表を自分の手で再現させる作業もおすすめです。 市販のかけ算カードをバラバラにして並べさせたり、空欄の九九表に答えを記入させることで、「ここにこの式がある」という視点で記憶が深まります。
また、九九表を防水タイプのものにしてお風呂に貼ったり、トイレや机の横に設置することで、目にする機会を増やし、無意識に情報を脳にインプットする環境づくりも有効です。
家庭でできる具体的な九九のサポート法7選
① リズムと音楽で楽しく記憶を促進する
九九を覚える際に、リズムや音楽の力は非常に大きな効果を発揮します。 特に耳からの刺激に強い子どもには、「九九のうた」やリズミカルな唱和が有効です。
YouTubeにはさまざまな九九ソングがアップされており、テンポや歌詞の違いで好みに合ったものを選ぶことができます。 歌詞を追いながら自然に口ずさむことで、反復のストレスなく覚えることができるのが大きなメリットです。
また、手拍子を打ちながら九九を唱えたり、音楽に合わせてジャンプするなど、身体的な動きを加えることで記憶がより強化されます。 音とリズムを組み合わせた遊び感覚の学習は、苦手意識のある子どもにも取り組みやすい方法です。
② カード・ゲームで「遊び感覚」の反復練習
子どもは遊びの中でこそ最も自然に学びます。 九九カードを使った「カルタ取り」や「ビンゴゲーム」、親子での「かけ算すごろく」などは、楽しみながら何度も九九に触れることができる定番のアプローチです。
また、九九カードを順番に出しながら「答えを当てるゲーム」をすると、テンポ感と正答率の向上につながります。 「◯の段だけで勝負」「今日は苦手な7の段だけに挑戦」など、ルールを工夫することで飽きずに続けることができます。
子どもが自分でカードを作るのもおすすめです。 書いて、切って、遊ぶというプロセス自体が記憶の定着に効果的で、愛着を持って学習できるようになります。
③ 日常生活と九九を結びつける「習慣化」戦略
九九の習得には「反復」が不可欠ですが、単調な学習にしないためには日常に溶け込ませる工夫が大切です。 たとえば、毎朝の支度のときに「3の段」、お風呂に入る前に「6の段」など、日々のルーティンに九九の練習を組み込むと自然に繰り返すことができます。
「1日1段、1週間で9段」にチャレンジする習慣も有効です。 日ごとの達成目標を小さく設定し、少しずつ成功体験を積み重ねることで、子どもの自信が育ちます。
また、買い物中に「リンゴが3個で100円、5袋買うといくら?」など、実生活の中で九九を応用させる声かけをすることで、九九の意味を理解しやすくなります。
九九が定着しないときの見直しポイントと追加対策
① 覚える方法が子どもに合っているか再確認する
九九がなかなか定着しないとき、まず見直すべきなのは「覚え方がその子の特性に合っているか」です。 音やリズムで覚えるのが得意な継次処理タイプなのか、それとも表や図などの視覚情報から覚える同時処理タイプなのかを見極めましょう。
「何度唱えても覚えられない」「言えるけど意味がわかっていない」「表を見てもピンとこない」などの様子が見られる場合は、方法が合っていないサインです。 一度立ち止まり、違うアプローチに切り替えることが、結果として近道になります。
また、苦手な段を無理に繰り返すのではなく、得意な段で自信をつけてから再挑戦する流れも有効です。 子どもが自信を失う前に、学習スタイルの再確認を行いましょう。
② 学習環境・時間・声かけを見直す
九九の定着には、学習そのものだけでなく、「環境づくり」も重要です。 まず見直したいのが、集中できる時間帯や場所の確保です。 テレビやゲームなどの誘惑が少ない時間に、静かで落ち着いた場所で学習できるようにしましょう。
また、親の声かけも大きな影響を与えます。 「なんでできないの?」「さっきも間違えたでしょ」といった否定的な言葉は、子どものやる気を奪う原因になります。
それよりも「昨日より速く言えたね」「さっきより間違いが減ったよ」と、プロセスを認める声かけを心がけましょう。 家庭の中に「間違えても大丈夫」という安心感があれば、子どもは自然と前向きに取り組めるようになります。
③ 習い事や支援サービスの活用も検討する
もし家庭でのサポートだけでは限界を感じるようであれば、外部の力を借りることも選択肢の一つです。 たとえば、オンライン教材や通信教育、学習支援系の習い事は、九九の定着に特化したプログラムを持っているところもあります。
ADHD傾向がある子どもや、集中力に課題のある子には、放課後等デイサービスや個別指導の塾など、専門的な支援を受けられる環境も有効です。 家庭と第三者のサポートを組み合わせることで、無理なく九九を習得する道が開けます。
大切なのは、「親がひとりで抱え込まないこと」です。 子どもにとって最適な環境を整えることが、ストレスなく学習を続けるための鍵になります。
まとめ:九九が覚えられない子にこそ“合った方法”が必要
九九を覚えられない子どもに対して、「何度も繰り返せばそのうち覚える」という一律の指導では、かえって学習意欲を低下させてしまうことがあります。 しかし、覚えられない背景には、必ず理由があり、それを理解し、寄り添うことが解決の第一歩になります。
本記事では、子どもの認知スタイルに合わせた「継次処理タイプ」「同時処理タイプ」それぞれのアプローチ方法、さらに家庭で実践できる7つの具体策、そして見直しのポイントまで詳しく解説してきました。
九九の学習は、子どもにとって初めての「暗記型の基礎学習」ともいえる重要なステージです。 ここで成功体験を積めるかどうかは、今後の算数、ひいては学習全体への自信に大きく影響します。
だからこそ大切なのは、「できない理由を見つけてあげること」そして「その子に合ったやり方で成功へ導くこと」です。 焦らず、怒らず、子どもと一緒に楽しく九九を乗り越える経験が、かけがえのない学びの土台になるはずです。
ぜひ、今日から始められる一歩を見つけ、少しずつ積み重ねてみてください。 子どもが「できた!」と笑顔を見せるその瞬間が、最大の成果です。