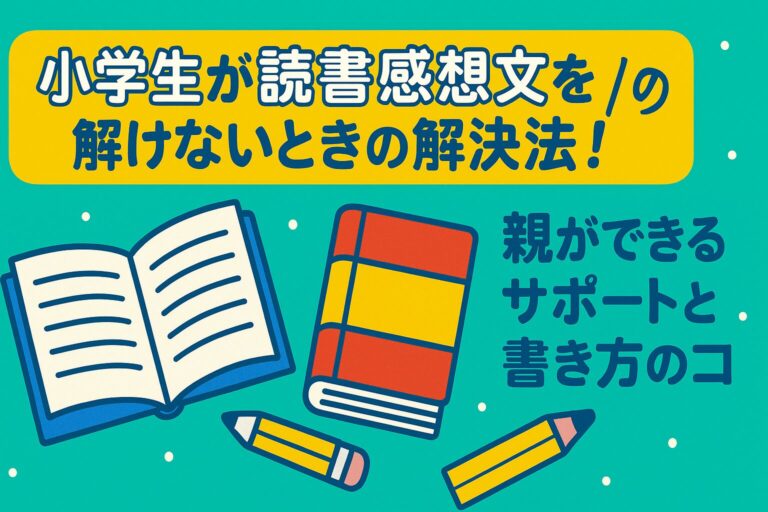夏休みの宿題の中でも、特に小学生を悩ませるのが読書感想文です。
「何を書けばいいのかわからない」「本は読んだけど感想が出てこない」など、子どもたちの戸惑いは多くの家庭で共通しています。
親としても、どうサポートすればいいのか悩み、気づけば親子ゲンカに発展してしまうこともあるでしょう。
本記事では、「読書感想文が書けない」と悩む小学生とその保護者に向けて、感想文を書くためのステップやサポートの仕方、効果的な会話術、書きやすくなるテンプレートなどを徹底解説します。
この記事を読むことで、お子さんが無理なく感想文を書けるようになり、親子で夏休みの宿題をスムーズに終わらせることができるようになります。
コンテンツ
読書感想文が書けない小学生に共通する3つの理由
1. 感想の言語化が難しい
小学生の多くは、本を読んで何かを感じていても、それを言葉にすることがまだ難しい段階です。
特に低学年では、気持ちをうまく表現する語彙が少なく、「おもしろかった」「たのしかった」だけで終わってしまいがちです。
この原因は、作文力の不足というよりも、気持ちを説明するための訓練が不足している点にあります。
だからこそ、「なぜおもしろかったのか?」「どの場面でそう思ったのか?」といった会話によって、子どもが自分の感じたことを少しずつ話せるように導く必要があります。
2. 読書感想文の「型」を知らない
読書感想文には、基本的な構成の「型」があります。
たとえば「本を選んだ理由 → あらすじ → 印象に残った場面 → 感想と自分の体験 → まとめ」といった流れです。
この型を知らないまま、いきなり自由に書かせると、何をどの順番で書けばよいのか分からなくなり、手が止まってしまいます。
まずは親がこの構成を把握し、子どもと一緒に「順番に中身を埋めていく」意識で進めると、驚くほど書きやすくなります。
3. 感想を引き出す質問が漠然としている
「どうだった?」「おもしろかった?」という質問だけでは、子どもは答えづらいものです。
「どの登場人物が好き?」「一番びっくりしたところはどこ?」「自分だったらどうすると思う?」など、具体的な質問に変えることで、子どもの中にある感情を言葉にする手助けができます。
特に、親子で一緒に本を読むことができれば、「今ここ読んでるね」「この人どう思う?」とリアルタイムで話せるため、自然と感想のストックが溜まっていきます。
小学生でも書ける!読書感想文の書き方ステップ
1. 本を選ぶ理由から始める
読書感想文は、本を選んだ理由を最初に書くことで、自然な導入が可能になります。
たとえば「表紙が面白そうだった」「友達にすすめられた」「動物の話が好きだから」など、どんな理由でも構いません。
ここで大切なのは、子ども自身の言葉で書くことです。
親が代筆したようなきれいな言葉よりも、「犬が好きだからこの本にした!」といった率直な表現のほうが、読書感想文として魅力的に映ります。
2. あらすじは短くまとめる
読書感想文の本題は「感想」ですから、あらすじは短くまとめるのがポイントです。
たとえば「〇〇という子が、△△で困っていたけれど、□□をして乗り越えた話」というように、3〜4行でストーリーの概要を伝えるだけで十分です。
親子で一緒に本を読んだ場合は、「この場面が一番大事そうだね」と一緒に話しながら要点を拾っていくと、あらすじも自然と短く整理できます。
また、感想文の中に登場人物の名前を数回出すだけで、読者にはその人物の印象が残りやすくなります。
3. 感じたことは「自分の体験」とつなげる
読書感想文で最も読みごたえがあるのは、「本の内容」と「自分の体験」が結びついている部分です。
たとえば「〇〇が友達とケンカして仲直りする話を読んで、ぼくも前に□□くんとけんかしたことを思い出しました」というように、自分の経験と本の場面を重ねて書きましょう。
この手法を使うと、読書感想文がぐっと深くなり、オリジナリティも生まれます。
親がサポートする際は、「似たようなことってあった?」「自分だったらどうした?」などの声かけが有効です。
読書感想文を書くときに役立つ親のサポート方法
1. 具体的な質問で感想を引き出す
子どもが「何も思わなかった」と答えるのは、感じていないのではなく、言葉にできないだけのことが多いです。
だからこそ「一番ドキドキした場面は?」「主人公の気持ちはどうだったと思う?」「自分だったら同じことをする?」など、具体的にイメージしやすい質問を投げかけることが効果的です。
また、選択肢を与える形で質問すると答えやすくなります。たとえば「この人は優しいと思う?それとも強いと思う?」と聞くと、子どもは比較して考えることができます。
その結果、単純な「おもしろかった」から一歩踏み込んだ感想が出てきやすくなるのです。
2. 子どもの言葉をそのまま尊重する
大人から見れば稚拙に思える表現でも、子どもにとっては大切な気づきです。
「すごい」「びっくりした」「かわいそうだった」といった言葉も、その背景を掘り下げれば立派な感想になります。
親が「もっとちゃんと書きなさい」と否定すると、子どもは書く意欲を失ってしまいます。
だからこそ「どうしてそう思ったの?」「どんなところがすごかったの?」と問いかけながら、子どもの言葉を膨らませてあげることが大切です。
3. 書く前に「話す」時間を作る
いきなり紙に書き出すのはハードルが高いため、まずは親子で話す時間を設けましょう。
「あの場面、面白かったよね」と親が感想を話すと、子どもも自然に「ぼくはそこよりも最後が好き」と言えるようになります。
つまり会話を通じて感想を言語化しておけば、作文にするときも書きやすくなるのです。
このプロセスを取り入れるだけで、子どもの負担は大きく減り、宿題がスムーズに進むようになります。
読書感想文がスラスラ書けるコツとテクニック
1. メモを取りながら読む
読書感想文を書きやすくするためには、読みながら感じたことをメモに残しておくのが効果的です。
「好きな登場人物」「びっくりした場面」「気持ちが動いたところ」などを簡単にメモしておくだけで、後から感想文に書く材料が揃います。
また、読んでいる最中に思ったことは鮮度が高いため、より生き生きとした表現ができます。
特に高学年になると、読書量が増えて話の内容を忘れやすくなるので、メモ習慣は非常に有効です。
2. 書き出しの定番フレーズを活用する
「何から書けばいいかわからない」という悩みを解消するには、定番の書き出しを用意しておくと安心です。
たとえば「私はこの本を読んで、〇〇だと思いました」「この本を選んだ理由は、□□だからです」という形です。
最初の数行さえスムーズに書ければ、その後の文章も流れるように進めやすくなります。
これは子どもだけでなく、大人でも文章を書くときに役立つ方法です。
3. 「起承転結」を意識する
感想文を書くときに起承転結を意識すると、まとまりが出て読みやすくなります。
起=本を選んだ理由、承=あらすじ、転=印象に残ったことと自分の体験、結=まとめという流れです。
この構成をベースにすれば、無理に難しいことを書かなくても自然な文章になります。
さらに、段落ごとに区切って書くと、見た目もすっきりして先生にとっても読みやすい感想文になります。
読書感想文を楽しく仕上げる工夫
1. 書きやすいテンプレートを使う
白紙からいきなり感想文を書こうとすると、子どもは何を書けばいいか分からなくなりがちです。
そこで便利なのが、あらかじめ「本を選んだ理由」「あらすじ」「心に残った場面」「自分の体験」「まとめ」といった枠を作ったテンプレートです。
この形式に沿って順番に埋めていけば、自然と感想文の形になります。
また、親子で一緒にテンプレートを見ながら進めると、子どもが安心して書けるため、宿題のストレスも大きく減らせます。
2. 親子で役割分担する
読書感想文は、必ずしもすべて子ども一人で完成させる必要はありません。
たとえば「本のあらすじは親が質問してまとめ、感想は子どもが答える」という形にすれば、作業がスムーズになります。
また、低学年の場合は親がメモ係を担当し、子どもが話した言葉をそのまま書き留めるのも有効です。
書く工程を共同作業にすることで、子どもが楽しんで取り組めるようになります。
3. 完成後は「がんばったね」と評価する
感想文は完成までに時間がかかるため、途中で子どものやる気が下がることも少なくありません。
だからこそ、仕上げた後に「よくがんばったね」「最後まで書けたね」と褒めてあげることが大切です。
大人から見れば短い文章でも、子どもにとっては大きな達成感になります。
その成功体験が次の学年以降の作文への自信につながり、結果的に文章力の向上にもつながっていきます。
まとめ
小学生が読書感想文を書けないのは、感想を言葉にする力や文章の型を知らないことが原因であり、決してやる気がないわけではありません。
だからこそ、親がサポートできるのは「感想を引き出す質問をする」「子どもの言葉を尊重する」「書きやすいテンプレートを用意する」といった工夫です。
さらに、メモを活用したり、定番の書き出しを使ったりすることで、子ども自身も安心して取り組めるようになります。
最も大切なのは、感想文を「苦しい宿題」ではなく「自分の気持ちを表現する体験」として楽しく感じられるようにすることです。
親子で協力しながら一つの作文を完成させることで、子どもにとっては達成感が生まれ、次につながる大きな一歩になります。
この記事で紹介した方法を取り入れて、ぜひお子さんが自分らしい言葉で感想文を書けるようにサポートしてあげてください。